本記事の目的
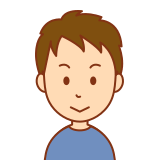
共通テスト倫理で高得点が取れないよ……。教科書の思想家やキーワードは一通りおさえたのに!
太郎君のような人、きっと受験生の中にもいますよね。「なんで共通テスト倫理で高得点取れないんだろう……」「共通テスト倫理は8割取って逃げ切りたいのに……」みたいな人、きっといると思います。このコーナーでは共通テスト倫理で9割を目標にして、どのように取っていくべきなのかを徹底的に解説したいと思います。
例題
自然についての様々な考えの説明として、最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
① プラトンは、現象界に現れているものはすべてイデアを原型とするものであるため、自然界の諸事物も真実在であるとした。
② アリストテレスは、自然の世界では、種子が樹木に成長するのと同様に、すべてのものは可能態から現実態へと展開すると説いた。
③ 欲望に対する理性の優位を説いたストア派においては、自然を支配する理法と人間理性とは別物であり、人は後者にのみ従うべきである。
④ キリスト教においては、自然そのものは悪であり、ユダヤ教では、自然界のすべてのものは、神によって創造されたと考えられている。
[センター試験2019本試験]
正答と解説
正答:②
それぞれの人物の考えを整理してみよう。
プラトン:現象界に現れているものはすべて「イデアの影」であり、真の実在(真実在)は「イデア界」に存在している。そのため、「自然界の諸事物も真実在」が誤り。詳しくはこちら。
アリストテレス:すべてのものは可能態から現実態へと展開する「目的論的世界観」である。詳しくはこちら。
ストア派:自然を支配する理法(ロゴス)と人間の理性は一致する(=人間は自然を支配する理法に従うべきである)そのため、「人は後者にのみ従うべきである」が誤り。詳しくはこちら。
キリスト教・ユダヤ教:自然そのものは悪ではなく善である(=自然界のすべてのものは神によって創造された)詳しくはこちら。
類題
問1 次の文章について、X・Yに適する語の組合せとして最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
古代ギリシアでは、自然現象を神々の力によって説明する時代を経て、人間の理性によって自然の秩序を理解しようとする思想が生まれた。その最初の哲学者とされる【 X 】は、万物の根源を水と考えた。やがて人々は、自然のうちに秩序と必然性を見いだす【 Y 】という考え方を通じて、神話的世界観から脱していった。
① X:タレス ― Y:ロゴス
② X:タレス ― Y:ミュトス
③ X:ヘラクレイトス ― Y:ロゴス
④ X:ヘラクレイトス ― Y:ミュトス
正答:①
解説:リード文を読んで解答する問題。この手の問題は基本的には易しいため、前後を確認して取りこぼしのないようにしたい。自然哲学では万物の根源だけでなく、その思想家の特徴も抑えておきたいところ。自然哲学については詳しくはこちらから。
ヘラクレイトスは万物の根源を火と捉えた。また、ロゴスは「論理、理法」などを表す言葉であるが、ミュトスは「神話」を意味する言葉である。古代ギリシア世界はこの頃に神話的世界観から合理的世界観に到達したことも併せて覚えておきたい。
問2 自然の成り立ちについて説明した思想家たちについて、最も適当なものを次の①~④のうちから一つ選べ。
① ピュタゴラス(ピタゴラス)は、万物の根源を火と考え、「万物は流転する」と述べた。
② デモクリトスは、万物の根源をアトム(原子)とし、世界は偶然の結合によってのみ成り立つと考えた。
③ パルメニデスは、変化や生成消滅を現実に起こるものとみなし、それが「あるもの」の本質であるとした。
④ エンペドクレスは、火・水・土・空気の四元素が混じり合い、愛と憎の力によって結合と分離を繰り返すと説いた。
正答:④
解説:共通テストでは正誤問題の判定が難しくなっている。思想家をキーワードとの関連で捉えるのではなく、根本的にどのような思想を有しているのかで捉えておきたい。自然哲学では万物の根源だけでなく、その思想家の特徴も抑えておきたいところ。自然哲学については詳しくはこちらから。
①:ピュタゴラスではなくヘラクレイトスの説明である。
②:「世界は偶然の結合によってのみ成り立つ」が誤りである。デモクリトスの原子論では自然法則(ロゴス)のもとに世界は成り立っている。
③:「変化や生成消滅を現実に起こるものとみなし、……」が誤りである。パルメニデスは変化や生成消滅の実在性を否定した人物である。
問3 古代ギリシアの思想家について、最も適当なものを次の①~④のうちから一つ選べ。
① ソクラテスは、「無知の知」とは、人間は何ものも真に認識し得ないという懐疑的立場を意味し、理性による真理探究はその認識によって真理が変わると考えた。
② プラトンは、「イデア」とは感覚的経験によって把握されるイデア界の形象を指すものであり、不変的なイデア界こそが理想の実在であるとみなした。
③ アリストテレスは、「中庸」とは極端を避けて平均的な態度をとることを意味し、理性のはたらきを伴わぬ安易な妥協として徳を理解した。
④ プロタゴラスは、「人間は万物の尺度である」と述べ、真理や価値の基準が個々人の主観的判断に依存するという認識論を提示した。
正答:④
解説:共通テストでは正誤問題の判定が難しくなっている。思想家をキーワードとの関連で捉えるのではなく、根本的にどのような思想を有しているのかで捉えておきたい。
①:「人間は何ものも真に認識し得ないという懐疑的立場」「理性による真理探究はその認識において真理が変わる」が誤り。ソクラテスの「無知の知」は無知を自覚することこそ真の知への出発点であるという意味である。またソクラテスは絶対的真理が存在するという立場に立っている。真理は相対的に変化しうるという立場はソフィストたちがとった立場である。詳しくはこちら。
②:「感覚的経験」が誤り。プラトンのいう「イデア」は人間の理性のみによって感じることができるもので、感覚的経験によって把握されうるのは現象界(現実世界)の「イデアの影」である。詳しくはこちら。
③:中庸とはバランスの取れた状態であり、「理性のはたらきを伴わぬ安易な妥協として徳を理解した」が誤り。詳しくはこちら。
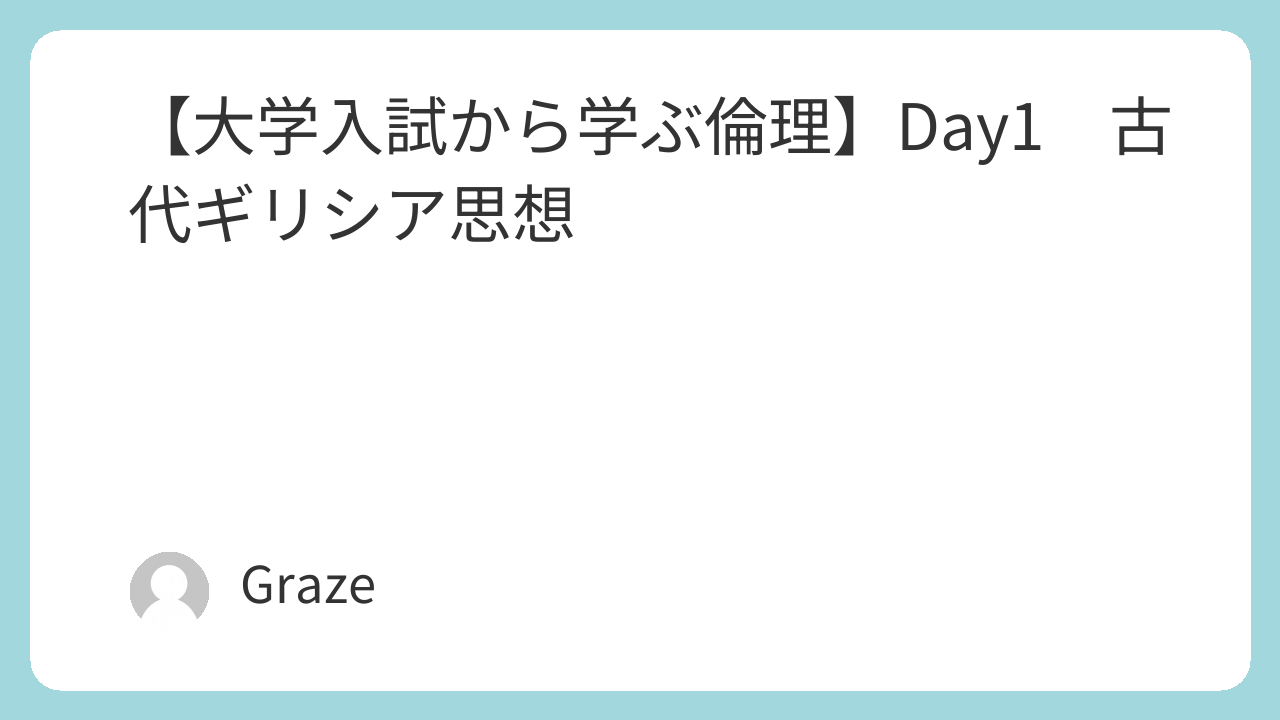
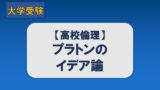
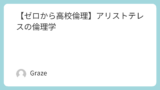
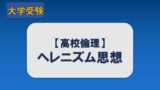
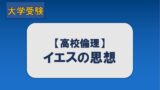
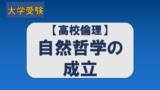
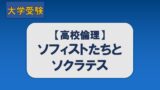
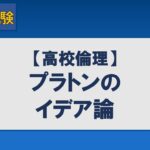
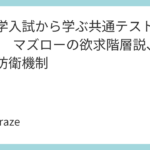

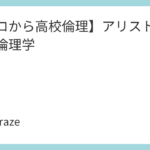
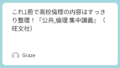
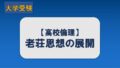
コメント