本記事の目的
最近の学習指導要領の審議ではよく「ギフテッド」と呼ばれる子どもに関する議論が進んでいます。しかし、日本ではギフテッドの知名度は残念なことにあまり高くはありません。おそらくこういう人が多いかと思います。
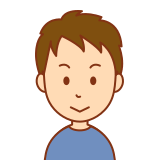
ギフテッドってどういう人のことなの?
そこで今回は「ギフテッドってどんな人のことなの?」という問いから出発し、「ギフテッド」に関わる教育の課題について、解説していきたいと思います。
ギフテッドってどんな人のことなの?
「ギフテッド」というのは英語で”Gifted”という綴りです。しかしながら、日本ではこの呼び名はあまり知られていません。そこで、次期学習指導要領の審議ではこの人たちは何と呼ばれているのでしょうか?
次期学習指導要領では「特定分野に特異な才能のある児童生徒」という表現をされています。例えばですが、小学校段階で高校範囲の数学を学んでいるというケースがこれに該当します。つまり、「どこかの分野で飛び抜けた才能のある子ども」を私たちは「ギフテッド」という通称で呼んでいるわけです。
なお、アメリカや韓国においてはすでにギフテッド教育が進んでいますが、IQ(知能指数)などで画一的に子どもたちをギフテッドとすることはありません。これはギフテッドとされた子どもたちに対していじめや差別を誘発するほか、特定の決まった値による線引きは不適当であると考えられているからです。
なぜ、「ギフテッド」の子どもたちの教育を考えなければならない?
実はこの「ギフテッド」と呼ばれる子どもたちは、学習上・生活上の困難を抱える場合があります。例えばですが、さっきの「小学校段階で高校範囲の数学を学んでいる」子どもであれば、「学校の授業が退屈だ」「友達と話が合わない」という困難を抱える場合が非常に多いです。
しかし、このギフテッド教育に関する議論は、令和4年12月に「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」の審議のまとめが発表されるまで、基本的な考え方すら提示されていませんでした。現在では、以下の基本的な考え方を提示しています。
① 多様な一人一人の児童生徒に応じ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の一環として、支援策を考える
② 特異な才能のある児童生徒が抱える学習上・生活上の困難に着目し、その解消を図るとともに、個性や才能を伸ばす
③国は、次期学習指導要領や環境整備などの制度的な改善についても、必要に応じて進めるべき
このような基本的な方針をもとに、令和5年度以降、文部科学省はギフテッドに関する事業を推進してきたのです。また、令和7年度の予算事業では、「地域レベルや全国レベルで、保護者や児童生徒を対象とした相談体制の構築」を推進しています。その他にも、ギフテッドの子どもたちの特性に応じた学びを提供するため、さまざまなプログラムを進めてきたのが現況です。
しかしそれでも、ギフテッド教育には大きな課題が存在します。一つ目は、ギフテッドの子どもたちの特性に応じた教育課程を作れる制度が存在しないという問題です。ギフテッドの子どもたちの習熟度に合わせるならば、例えば小学校段階で高校数学を取り扱うという教育課程を作るのがベストな選択肢です。
このような教育課程を「特別の教育課程」と呼びますが、この制度が存在しません。制度として存在しない以上、どのような教育プログラムを考えたところで公的な教育課程としては(少なくとも制度上は)認められないのです。
これは極めて大きな問題です。なぜならば、特別の教育課程の制度が存在しないという状況によって、ギフテッドの子どもたちは「学ぶ場」を失うことになっているからです。言葉を選ばずに言えば、公教育制度からギフテッドの子どもたちを排除していると受け取られても仕方ありません。
また、ギフテッドの子どもたちの特性に応じた適切な学びにつなげていくための相談支援体制は、未だ確立できていません。ギフテッドの子どもたちの現状としては、あまり明るいものではありません。
今後の見通し……
次期学習指導要領の審議も本格的に進み、ギフテッド教育に関する審議も2回目を数えています。その2回目の審議では、諸外国におけるギフテッド教育に関する検討が付されました。我が国のギフテッド教育はどのように進んでいくのか、教育に興味のある人であれば注目に値するトピックです。
今後も次期学習指導要領の審議について、随時解説記事にします。そこから日本の教育の現状を探っていきたいと思います。では、また次回の記事で!
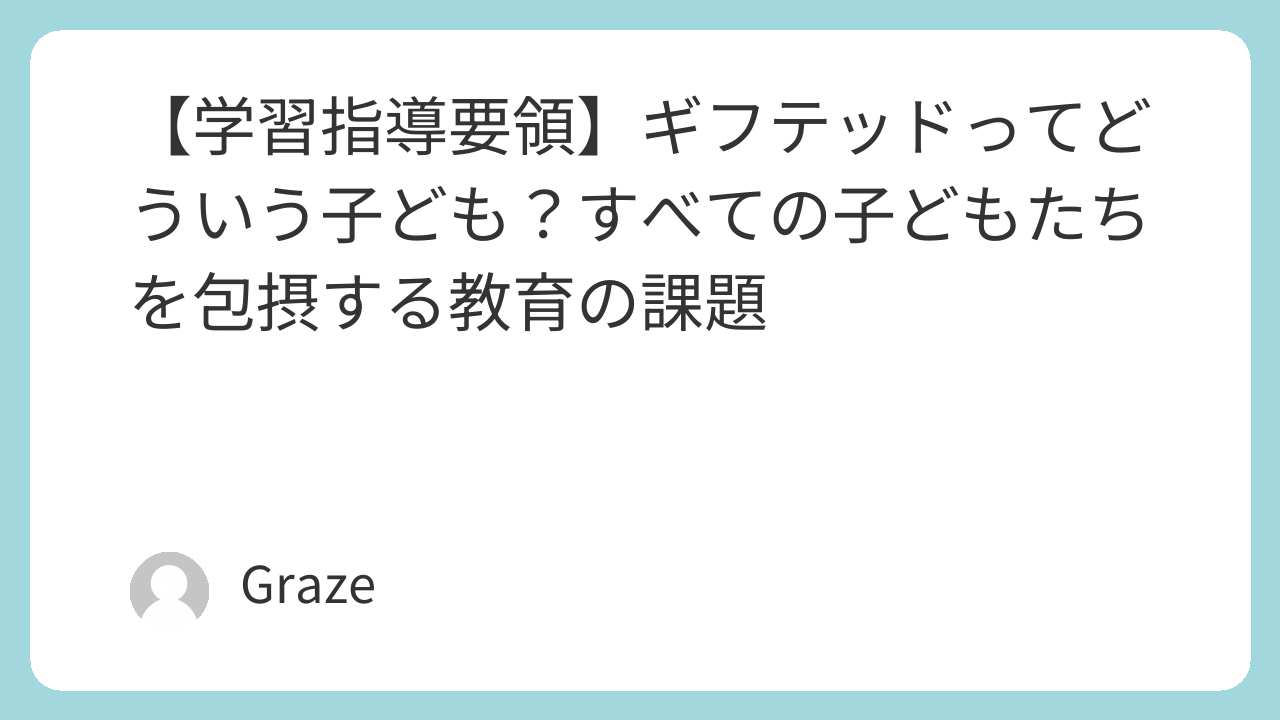

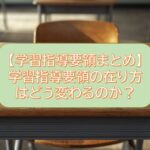
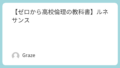
コメント