このページを読むとわかること
このページを読むことで、以下のことがわかるように書かれています。
- 2030年の学習指導要領の改訂での子どもたちに求められる資質・能力
前回の復習
- 現行の学習指導要領では能動的に学ぶ「主体的・対話的な深い学び」の実現をめざしている
- 子どもたちの学んでいることへの目的意識に課題があるとされている
- 学習指導要領ではすべての子どもたちを包摂することが必要である
参考資料
次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ(文部科学省)リンク
学習指導要領の目指すべき姿はどこにあるの?
学習指導要領は全国のどの学校にも適用される、教育課程の最低基準を定めたものであるというのは前々回にもお話ししましたが、学習指導要領は何を目標としているのでしょうか。
これについては、必ず触れなくてはならない法令があります。それが教育基本法という法律です。この教育基本法において、第1条で定められている内容が次のものです。
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
つまるところ、教育が目指すべき姿は子どもたちの「人格の完成」にあり、学習指導要領はそのための最低基準を定めているということになります。また、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた」というところもキーワードになります。このような子どもたちを私たちは育てていきたいわけなのです。
生きる力って何だろう?
そこで、文部科学省は「生きる力」という概念を提唱するわけです。これについては、「変化の激しいこれからの社会を生きていくために必要な資質・能力の総称」として捉えられています。しかしながら、この概念は決して新しいものではありません。平成8年7月の中央教育審議会(中教審)の答申において、この「生きる力」について位置づけられています。
しかしながら、現在においても変化の激しい社会である以上、この「生きる力」は重要な能力・資質となるわけです。そこで、大切にされなければならないのはこの「生きる力」は「どのような能力なのだろうか?」という点です。これについて「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」では、以下のような例を挙げています。(重要な箇所は太字にしています)
- 社会的・職業的に自立した人間として、我が国や郷土が育んできた伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持って、主体的に学びに向かい、必要な情報を判断し、自ら知識を深めて個性や能力を伸ばし、人生を切り拓いていくことができること。
- 対話や議論を通じて、自分の考えを根拠とともに伝えるとともに、他者の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、集団としての考えを発展させたり、他者への思いやりをもって多様な人々と協働したりしていくことができること。
- 変化の激しい社会の中でも、感性を豊かに働かせながら、よりよい人生や社会の在り方を考え、試行錯誤しながら問題を発見・解決し、新たな価値を創造していくとともに、新たな問題の発見・解決につなげていくことができること。
生きる力を身につけるために、すべての教科でできることは?
実は、現行の学習指導要領においては「言語活動の充実」を各教科を貫く「改善の視点」として掲げています。しかしながら、現状としては「思考力の育成に一定の成果はあるけども、まだそれが一貫しているわけではないね」という感じです。
ところで、ここまで説明していなかった概念について、今更ながら触れておきます。それは「教育課程」という言葉についてです。簡潔に言えば、学習指導要領は最低基準の教育課程となっています。そして、教育課程とは「どの内容を、どの教科で、どのように指導するか」というものを定めたものです。そして先に述べた「言語活動の充実」は教育課程全体における「改善の視点」となっています。
そして、教育課程全体として言語活動の充実を改善点として示しているものの、それを全ての教職が意識できているわけではありません。もっと言えば、教職が授業について考えるとき、まずは「何を教えるか」を意識しています。
言語活動の充実だけをすればよいのか?
そもそもですが、授業をどのように展開していくかという指導法は、その授業にきちんとした内容が詰められていることが前提となっています。何も教えることがないのに、言語活動を充実させるだけでは思考力の育成には繋がらないのです。そのため、まずは内容について考える教職が多いです。もちろんですが、子どもたちの時間には限りがありますので、教科書・資料集で扱っているすべての内容について、グループ活動などを行うことはできません。これらをふまえた上で、教職は「何を、どのように教えるのか」を考えています。
しかしながら、ここにも教職の技量という限界があります。例えばですが、社会科で選挙のトピックを扱うとしましょう。選挙のトピックといっても、様々な切り口がありますから、ひとまず私が思いつく分をリストアップしてみましょう。
- 直近に選挙があった場合、ニュースなどを見せて選挙への関心を向ける
- 生徒会選挙を通して、公平な選挙に必要な条件を考えさせる
- 架空事例を通して、選挙で当選する人を決めさせる
- 架空事例を通して、メディア・リテラシーについて考えさせる
※メディア・リテラシーとは、メディアを正しく活用する能力を指します。
全部をリストアップしていてはきりがないので、ひとまずはここまでとします。私は今これだけの授業の仕方を思いつくわけですが、これはその教職のキャリアや技量に依存します。実際にあった話ですが、私が教育実習でお世話になっていた先生は、ある1本の動画を見せて、メディア・リテラシーの重要性を子どもたちに気づかせるという授業を展開していました。このような手法は、(特に授業ネタが豊富でない若手にとっては)なかなか考えられないでしょう。
また、上にリストアップしたような授業が必ずしもできるとは限りません。それは子どもたちの実態や教職の技量によって、授業の質が変わることもさることながら、言語活動(グループワークやディベートなど)を取り入れた授業がイメージしにくく、難しいということも挙げられます。だからこそ、言語活動の充実が「改善の視点」として掲げられているわけです。
もちろんですが、言語活動の充実は先に述べたような子どもを育成するためには必要な条件です。そのため、言語活動の充実を手段として捉え、子どもたちにどのような能力・資質を身につけさせるかが重要な論点となっているのです。
本記事のまとめ
ここまで、2030年の学習指導要領の改訂での子どもたちに求められる資質・能力についてまとめていきました。では、今回のまとめをしましょう。
- これからの変化が激しい社会に対応するための「生きる力」をどう捉えるべきか?
- 対話や議論などの言語活動を通して、どんな子どもたちを育てていくべきか?
- 言語活動の充実が目的になってはいけない。どのような教育も完成形は「人格の完成」であり、「これからの社会の担い手」を育てていくことである
次回は、こうした教育課程を社会全体で共有していくためには、どのような課題があるかについて見つめてみましょう。
では、次の記事をお楽しみに!


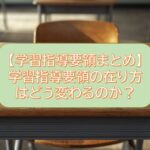
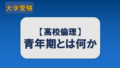
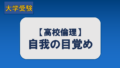
コメント