このページを読むとわかること
このページを読むことで、以下のことがわかるように書かれています。
- 教職目線での2030年の新学習指導要領の大きな変更
前提知識
この記事では前提知識として、次のことを知っている前提でお話を進めていきます。
- 学習指導要領は教育課程の最低基準を定めるものである
- 学習指導要領には10年に1度大きな改訂が入る
もし、「わからないよ~」という方がいれば、こちらの記事で学習指導要領について詳しく説明しています!ぜひご覧ください!
現在の学習指導要領の課題
現在の学習指導要領では、今なお次のような課題が残っているとされています。
- 子どもをどのように育てるか?どのような能力・資質を育むかの具体化が必要である
- 「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力、人間性等」の3つの資質・能力が、相互にどのように関わっているのかがわかりにくい
- 未だ抜け出せない「教科書主義」……教科書「を」教える現場が未だに少なからず存在する
これだけ述べてもなかなかわかりにくいと思いますので、これから具体例をお話していきます。
実際の現場では……
これはある教職が実際に経験した話だとされています。
その先生は初年度で地理総合と地理探究を担当することになりました。しかし、その先生の専門は世界史だったのです。(実は4年ほど前までの学習指導要領では、地理を履修しなくても高校を卒業することができましたが、現在では地理総合が高校を卒業するうえで必修となっています)
当然ですが、地理の学習指導要領などについては、そもそも大学の講義で扱った程度の話しか知りません。そのため、初年度で地理を担当するのがわかった時点で、その先生は学習指導要領を読み込むことを始めました。
しかし、何ということでしょう。学習指導要領を読んでみても、どのような授業をすればいいのかがわかりませんでした。結局のところ、教科書と指導書を読み込み、さまざまな地理の授業を参考にしながら授業づくりを進めることとなったのです。
現在の学習指導要領は、言うなればゴールの旗だけが立っている真夜中のレース場です。「このような子どもを育てたいよ」という最終目標は、これまでの教育的課題をふまえれば明らかでしょう。しかし、そこまでにたどり着く道は示してくれません。
最終目標だけがあっても、その手段や中間目標がなければ絵に描いた餅です。もちろん、それにナビゲーションがついても教職は現場では多々悩むことがあるでしょうが、それでも何もないよりははるかにマシです。
もう一つお話をしてみましょうか。地理総合では「GIS(地理情報システム)を活用せよ」という留意点がほとんどの科目にくっついています。しかし、ある先生が教科の会議で聞いた話は、にわかには信じられないものでした。
「おそらくうちの生徒のChromeBookだと、GISは動かないと思います」
これは実際のところ誤解でした。実際に使ってみたところ、「まあ動く」程度ではあったようです。しかしながら、学習指導要領において指導上の留意点として強調されているにもかかわらず、「まあ動く」程度では困ります。結局そのChromeBookを酷使しながら、GISを用いて授業していたそうです。
このように、現場には現場の実態があります。最終目標だけがある学習指導要領もとても困りますし、そこまでに行き着くまでに現場によって様々な制約があるというのもとても困ります。そんな中で学習指導要領、教科書と指導書(場合によっては資料集も)だけで最終目標まで突っ走るのは難題です。しかも、そのような授業は往々にして教科書「を」教える授業になりがちなのです。
次の学習指導要領ではどうなる?
ここまで現在の学習指導要領の課題をお伝えしましたが、ついにこの部分にテコ入れされます。
まずは、各教科の中核的な概念等について、「構造化」されます。
※「中核的な概念の深い理解」「複雑な課題の解決」を以下、中核的な概念等と表記します。
そもそもですが、学習指導要領(特に解説が含まれている方)はすごく長いです。本当に。高校の地理歴史に関しては、付録を除いても360ページ近くあります。とてもじゃないですが読めません。しかも、似た内容が重複して書かれていることもあります。
しかも内容もすごく多いです。とくに歴史総合。70時間で出来るような量ではありません。70時間でやる場合、相当教科書から内容を削り、一つのテーマを貫徹しなければ不可能に近いです。もちろんそれを求めているんでしょうが、それにしても多すぎます。
そのため、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、各教科の中核的な概念等の獲得に重点を置くために必要な学習内容を検討したり、必要に応じた精選を行う方向で検討すべきとされています。
さらに、基礎的・基本的な内容についてもテコ入れがされます。認知心理学等の観点から、個別の知識の集積に止まらない概念としての理解や意味理解を含む「深い学び」を促す指導に関する検討が付されるそうです。これについては各教科部会で検討に付されるでしょうから、それを待ちましょう。
また、学習指導要領が表形式化される方向性で進んでいるそうです。これは単純に冗長な記載や複雑さの改善でしょう。学習指導要領が見やすくなるのはすごく助かります。本当に。
さらに大きな変更です。一人ひとりの教師について「デジタル学習指導要領」なるものを利用できるようにするということらしいです。これについてはおそらく漸次的に進んでいくでしょう。もちろん速ければそれに越したことはないですが。ちなみにこの「デジタル学習指導要領」はこのようなことができるそうです。
- 教科等間の関係、学年段階や学校種間の記載が容易に俯瞰できる
- 学校指導要領コードも活用し、学習指導要領とデジタル教科書・教材を紐づけることにより、相互のアクセス等が一層円滑となる
- AI等の活用により、日々の授業づくりに関わる疑問に対するフィードバックを受けたり、指導案のたたき台等の作成が容易になる
これは……扱う教職にも技量が問われる学習指導要領になりそうですね。個人的には教科等間の関係や学年段階、学校種間の記載が俯瞰できるのがすごくポイント高いです。毎回付録まで目を通すのは疲れますからね。教員免許を持っている科目であればまだ内容は頭に入っていますが、他科目の内容までは目を通せませんから。
まとめ
いつも通り、本記事のまとめといきましょう。
- 現在の学習指導要領は最終目標はしっかりしているけど、それまでの過程がわかりにくい
- 次の学習指導要領では内容が精選され、構造化される!
- 見にくかった学習指導要領が表形式化される!
- 「デジタル学習指導要領」がどのように実装されるか? →今後も注目が必要。
ということで、次回の記事でまたお会いしましょう!
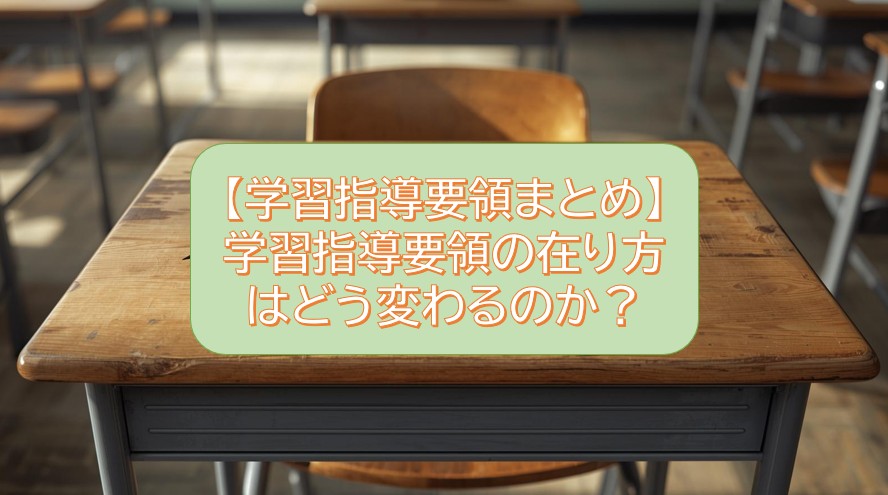

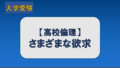
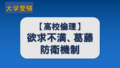
コメント