この記事が対象としている方
- 共通テストで倫理を使う受験生
- 定期テストや日常学習で倫理を勉強している高校生
青年期の発達に関する共通テスト風問題
今回は、教科書「青年期とは何か」の内容をもとに、共通テストっぽい正誤問題を作成しました。どの選択肢も一見正しそうに見えるものばかり。用語の対応や心理学者の説明のズレに注意して解いてみましょう。
第1問
次の文章は、青年期に関する説明である。誤っているものを1つ選べ。
① ルソーは、思春期における自我のめざめを「第二の誕生」と呼び、精神的成長の重要性を説いた。
② ホリングワースは、青年期を「心理的離乳」の時期と呼び、親からの精神的自立を強調した。
③ エリクソンは、青年期を心理社会的モラトリアムの時期とし、社会的役割を猶予された期間とした。
④ アリエスは、近代以前の子どもを「小さな大人」と呼び、近代的学校制度の成立によって青年期が失われたと述べた。
▶正答:④
▶解説:アリエスは「近代以前の子どもは小さな大人とみなされていた」と述べたが、近代的学校制度の成立によって青年期が出現したと考えた。
第2問
次の文章は、「マージナル・マン(境界人)」に関する説明である。明確に誤りであるものを1つ選べ。
① マージナル・マンとは、複数の文化や集団に属することで心理的に安定する青年のことを指す。
② レヴィンは、マージナル・マンをいずれの集団にも安定した帰属意識を持てず心理的動揺を経験しやすい存在とした。
③ 「疾風怒濤の時代(シュトゥルム・ウント・ドラング)」は、ホールが青年期の激しい情動を象徴する言葉として用いた。
④ クーリーは、他者の反応を通して形成される自己像を「鏡映的自己」と呼んだ。
▶正答:①
▶解説:①は誤り。マージナル・マンはむしろ心理的に不安定な存在である。
第3問
次の文章は、青年期の心理的特徴に関する説明である。誤っているものを1つ選べ。
① エリクソンは、モラトリアムの時期を「人生の実験室」と呼び、青年が役割実験を通して社会的な自分を探す期間とした。
② 小此木啓吾は、自由で心地よいモラトリアム状態にとどまり続ける青年を「モラトリアム人間」と呼んだ。
③ 「ピーターパン・シンドローム」や「青い鳥症候群」は、社会参加を積極的に進める青年の理想主義を指す言葉である。
④ 知識や技術の高度化により、青年期のモラトリアム期間は現代社会では延長される傾向にある。
▶正答:③
▶解説:「ピーターパン・シンドローム」や「青い鳥症候群」は、むしろ社会的成熟を回避する傾向を指す。
第4問
次の文章は、社会性や道徳性の発達に関する説明である。それぞれの文の正誤を答えよ。
A ピアジェは、具体的操作期において脱中心化が進み、他者の立場から考えることができるようになるとした。
B ピアジェは、道徳的判断が「行為の結果」から「意図や動機」へと発達していくことを明らかにした。
▶正答:A:正しい B:正しい
▶解説:正答の通り。
第5問
次の文章は、「愛着」や「友情」に関する説明である。誤っているものを1つ選べ。
① ボウルビィは、人間には特定の他者との近接を求める傾向があり、これを「愛着(アタッチメント)」と呼んだ。
② 青年期になると、愛着の対象は養育者から友人・恋人へと移行する傾向がある。
③ ショーペンハウアーの「ヤマアラシのジレンマ」は、相手を傷つけることを恐れず、過度に親密な関係を結ぶ青年を批判したものである。
④ アリストテレスは、友情を「もう一人の自己」と表現し、人間関係の重要性を説いた。
▶正答:③
▶解説:「ヤマアラシのジレンマ」は、相手を傷つけることを恐れるあまり距離を取ってしまう青年の葛藤を表している。
まとめ
- ルソー:「第二の誕生」=思春期の自我のめざめ
- エリクソン:「心理社会的モラトリアム」=人生の実験室
- レヴィン:「マージナル・マン」=心理的に不安定な青年
- ピアジェ、コールバーグ:社会性・道徳性の発達段階
- ボウルビィ・アリストテレス:愛着と友情の心理
「用語を覚えるだけでなく、誰がどの文脈で使ったのか」を整理しておくと、倫理の問題はぐっと解きやすくなります。共通テストまであと二か月です。点数を取りに行きましょう!
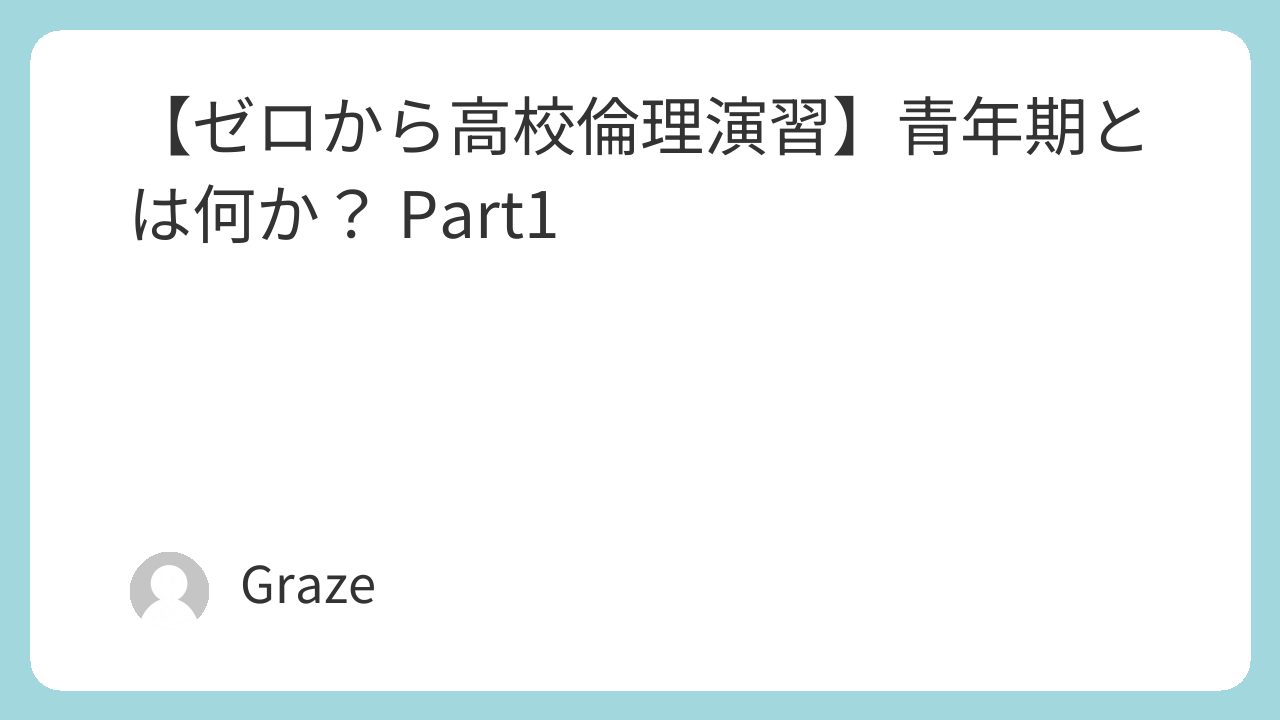

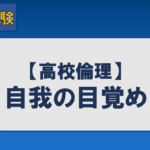
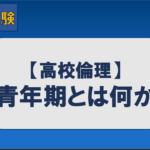
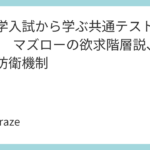


コメント