この記事が対象としている方
- 大学入試で倫理を受験科目とする人
- 世界史や宗教の内容を関連づけて理解したい高校生
- キリスト教の成り立ちや思想が、どのように成り立ったのかを知りたい人
前回はイエス=キリストの思想について解説しました。まだ見ていない方はこちら。
【この記事のキーワード】
イエス、受難と復活、パウロ、信仰義認、原罪、三元徳、アウグスティヌス、恩寵、スコラ哲学、トマス・アクィナス、理性と信仰
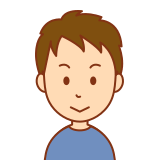
原始キリスト教がどのようにして成立して、発展していったのかを学んでいきます。
イエスの受難と復活 ― キリスト教の原点
紀元1世紀、ユダヤの民の中に現れたイエスは、神の前で人間は皆平等であり、愛と赦しによって人々は救われると説きました。しかし、この教えは既存の宗教的権威――ユダヤ教の指導者層――を脅かすものでした。指導者たちはローマ総督ピラトに訴え、イエスは十字架刑に処されます。これが「受難」です。
けれども物語はここで終わりません。弟子たちは当初、迫害を恐れて散りましたが、やがてイエスの「復活」を証言し始めます。彼らは、イエスの死が神の愛のしるし――すなわち、人間の弱さや苦しみを引き受けた神の救いの行為――であると理解したのです。ここに、イエスが「全人類の救い主=キリスト(メシア)」とされる信仰の基礎が生まれました。
パウロの回心と「信仰義認」
キリスト教が世界宗教として広まる契機をつくったのが、使徒パウロです。もともと熱心なユダヤ教徒で、律法の遵守こそ救いへの道と考えていた彼は、あるとき「ダマスコ途上の回心」と呼ばれる体験を経てキリスト教徒となりました。
パウロは「誰もが原罪をもって生まれる」と考え、その罪をイエスが身代わりとして背負ったと理解します。つまり、救いとは人間の行い(律法の実践)ではなく、キリストへの信仰によって与えられるものなのです。これを信仰義認と呼びます。
パウロはさらに、ユダヤ人・異邦人・男女などの区別を超え、すべての人が信仰によって「神の前に平等」であると説きました。この思想は後に「隣人愛」や「人権」などの普遍的価値観へとつながっていきます。彼の教えの中心には「信仰・希望・愛」という三元徳があり、それを身をもって示しながら各地を巡って伝道を続けました。
迫害から公認へ ― 教父たちの哲学的展開
キリスト教は当初、ローマ帝国の中で厳しい迫害を受けました。けれども信徒は増え続け、4世紀にはついに公認され、やがてローマ帝国の国教となります。この過程で登場したのが「教父」と呼ばれる人々です。彼らは、ギリシア・ローマ哲学を取り入れながら、キリスト教を知的体系として整備しました。
なかでも重要なのが「三位一体」の教義――父なる神・子なるキリスト・聖霊は本質において一つである――という考え方です。この教義は、神の存在と人間の救いを理論的に説明しようとする試みの中心でした。
アウグスティヌス ― 恩寵と神の国
教父の中でも最も大きな影響を与えたのがアウグスティヌスです。彼は『告白録』『神の国』などの著作を通して、「人間は本質的に罪深い存在であり、神の恩寵(恵み)によらなければ救われない」と説きました。これは恩寵予定説とも呼ばれ、救いが神の意志によってあらかじめ定められているという考えです。
彼はギリシア哲学の四元徳(知恵・勇気・節制・正義)の上に、キリスト教的三元徳(信仰・希望・愛)を置き、信仰をもとに神と人の双方に対して正しく生きることの大切さを説きました。新プラトン主義の影響を受け、地上の国の上に「神の国」があるとし、教会を神の救いの入り口とみなしました。
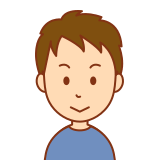
アウグスティヌスは、現実の社会や国家を「地上の国」として批判的に捉えた点でも重要ですね。
スコラ哲学 ― 理性と信仰の調和
中世ヨーロッパでは、12世紀以降に大学が設立され、学問の中心として神学と哲学が発展します。この時期の思想を「スコラ哲学」と呼びます。スコラ哲学の目的は、信仰と理性を調和させることでした。そのために、哲学を用いて神学を分析したのです。
トマス・アクィナスはその代表的思想家で、『神学大全』においてアリストテレス哲学を用いながらキリスト教の教義を体系化しました。彼は「神によって啓示される真理は理性を超えるため、理性の真理と矛盾しない」と述べ、信仰と理性の調和を重視しました。また、世界は神の永遠の法(自然法)によって支配されており、それが人間社会の根本規範であると説いたのです。
一方で、ウィリアム・オッカムは「信仰は理性では証明できない」として、信仰と理性を分離しました。これが後のスコラ哲学の衰退につながっていきます。
学習のヒント
学習のヒント!
- パウロの「信仰義認」は宗教改革ともつながる。信仰によって救われるという考え。
- アウグスティヌスの「神の国」は、国家や法の正当性を考える上でも重要。
- スコラ哲学は「信仰と理性の調和」をめぐる典型例。近代合理主義への前提となる。
まとめ
- パウロ:「信仰によって義とされる」ことを説き、普遍宗教へ
- アウグスティヌス:恩寵と神の国の思想で中世思想を確立
- トマス・アクィナス:信仰と理性の調和を図り、神学を体系化
- オッカム:信仰と理性の分離を唱え、近代思想へ道を開く
イエスの復活から始まった原始キリスト教はこのようにして発展していきました。ここまでの流れをストーリーとして記憶しておくことで、「誰がどのような思想を有していたか」がわかりやすくなります。
次回はキリスト教を離れてイスラーム教の解説をします。次回もお楽しみに!
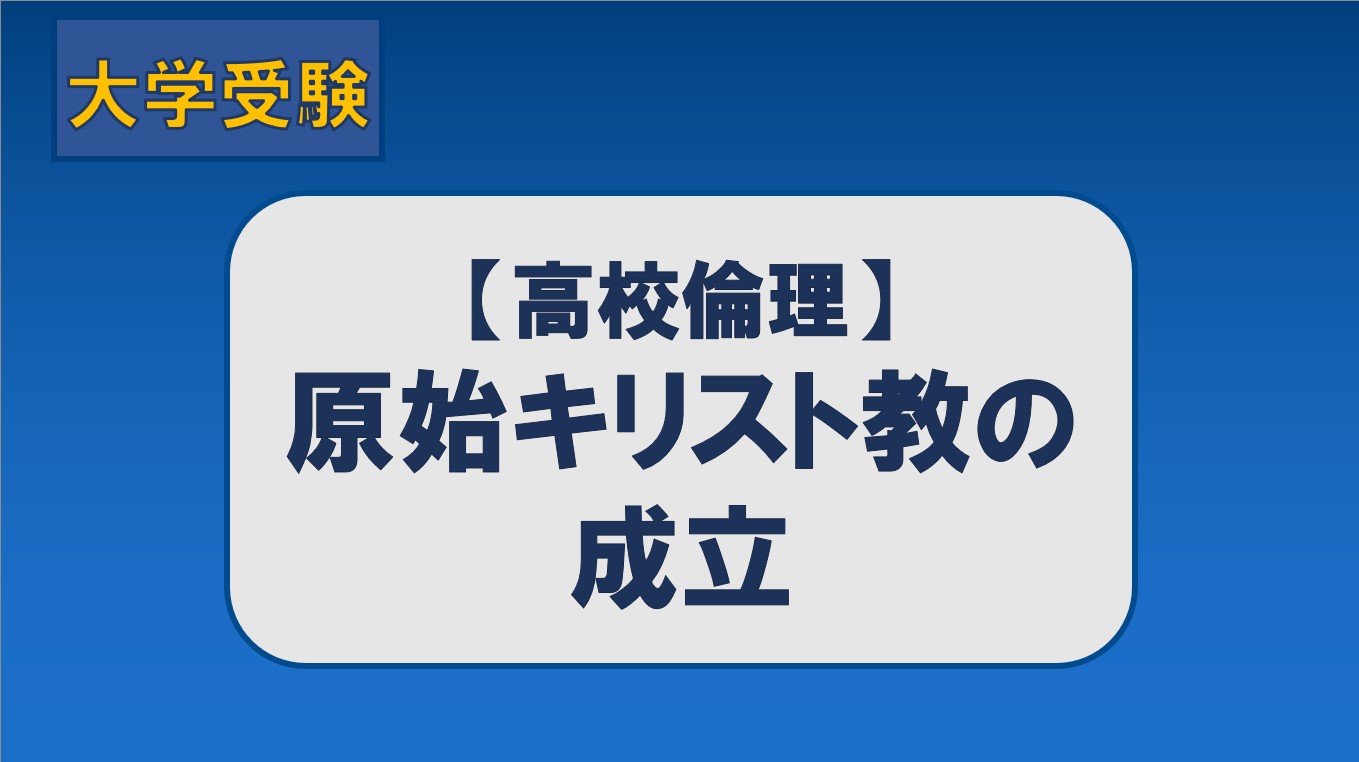
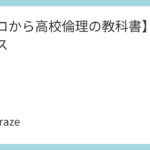
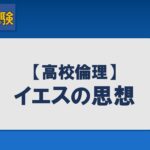
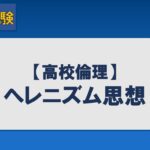
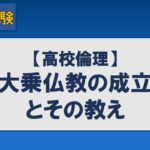
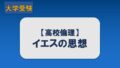
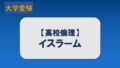
コメント