この記事が対象としている方
- 大学入試で倫理を使う受験生
- 定期テストや日常学習で倫理を勉強している高校生
- 孟子・荀子・朱子・王陽明など、儒家思想の流れを体系的に理解したい人
【この記事のキーワード】
孟子、性善説、四端の心、浩然の気、王道政治、易姓革命、荀子、性悪説、礼治主義、朱子学、理気二元論、陽明学、良知、知行合一
前回は孔子の「仁」と「礼」について学びました。リンクはこちらから。今回は、その教えを受け継ぎながら展開していった儒家思想の発展をたどります。孟子・荀子から、宋代の朱子・明代の王陽明へと続く流れを整理し、入試でも頻出の思想を体系的に理解していきましょう。
例題 ―このレベルの問題が解けるようになればOK!
今回はこのレベルの問題を解けるようになりましょう。
X
人間は本来、他者を思いやる心を備えており、そこに善の萌芽を見出すことができるとした。しかし、その心が外界の誘惑によって曇ることもあるため、徳の涵養によって本性を磨くことが重要だと説いた。
Y
人間の心は宇宙の理と一体であり、外に真理を求めるのではなく、自らの心に潜む理を明らかにすべきだと考えた。知ることと行うことは本来分かちがたく、実践によってこそ真の知が成立するとした。
Z
社会の安定は人々が互いに利害を調整し、共に利益をもたらす関係を築くことによって成り立つと考えた。そのため、すべての人を平等に愛し、争いを避けることで平和が実現すると説いた。
① X:孟子 Y:朱子 Z:韓非子
② X:孟子 Y:朱子 Z:墨子
③ X:孟子 Y:王陽明 Z:韓非子
④ X:孟子 Y:王陽明 Z:墨子
⑤ X:荀子 Y:朱子 Z:韓非子
⑥ X:荀子 Y:朱子 Z:墨子
⑦ X:荀子 Y:王陽明 Z:韓非子
⑧ X:荀子 Y:王陽明 Z:墨子
正答:④
解説はこの記事をご覧ください!
孟子 ― 性善説と王道政治
孔子の後継者として儒学を発展させたのが孟子です。彼は人間の本性を「善」とする性善説を唱えました。孟子によれば、すべての人は生まれながらにして善を実現する可能性をもっていますが、それを育てるかどうかは本人の努力次第だとされます。
孟子は、人の心には生まれつき次のような四つの「善の芽(四端)」があると説きました。
- 惻隠の心:他人をあわれみ、いたむ心
- 羞悪の心:悪を恥じ、正義を求める心
- 辞譲の心:他人に譲り、へりくだる心
- 是非の心:善悪や正邪を判断する心
この四つの心を育てることで、「仁・義・礼・智」の四つの徳が実現されると孟子は考えました。つまり、人は本来、善を求める心をもつ存在であり、それを失わないように努力することが大切なのです。
孟子はまた、強い精神力をもって正義を貫くことを「浩然の気」と呼びました。天地に満ちあふれるような正しい気を養い続けることで、真に勇気ある人物――「大丈夫」になれるというのです。彼にとっての理想の人間像は、内面に確かな徳を備え、外からの圧力に屈しない人格者でした。
政治についても孟子は「仁義に基づく政治」、すなわち王道政治を説きました。為政者(王)は武力や恐怖で民を支配するのではなく、徳をもって人々の幸福をはかるべきだとしたのです。そして、もし支配者が徳を失い民意に背くならば、その地位を失うことも正当だとされました。これが易姓革命の思想です。「天命」を失った王は廃され、新しい徳のある王が立つ――孟子はこのように、政治の正当性を「徳」に求めたのです。
荀子 ― 性悪説と礼治主義
一方、同じ儒家の思想家でありながら、孟子とは正反対の立場をとったのが荀子です。彼は人間の本性を「悪」とする性悪説を唱えました。ここで言う「悪」とは、暴力的な意味ではなく、「人は放っておくと利己的になり、欲望のままに行動してしまう」という現実的な見方を指します。
荀子によれば、人が善を行えるのは、後天的に教育や規範によって矯正されるからです。つまり、道徳は生まれつき備わっているものではなく、学びと努力の結果として身につくものだと考えました。この立場は、教育の重要性を強調する思想として、現代にも通じるものがあります。
社会の秩序を保つためには、人々が欲望に流されないように、一定のルールが必要です。荀子は、孔子が重んじた礼を政治の中心に据える礼治主義を主張しました。秩序と礼節に基づく統治こそが、人間社会を安定させる道であるという考え方です。
孟子が理想とした王道政治を支持しつつも、荀子は現実的な政治(覇道政治)も必要に応じて容認しました。人間の弱さを見つめたうえで、規律と教育によって社会を整える――荀子の思想は、より現実主義的な儒学の方向性を示したといえるでしょう。
朱子学と陽明学 ― 儒学の完成と新たな展開
時代が下り、儒学は中国の国家思想として体系化されていきます。前漢の時代には五経(『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記』)が重んじられ、やがて宋代には孔子と孟子の教えを中心とする新しい学問が生まれました。それが朱子(朱熹)による朱子学です。
朱子学の根本は、宇宙を構成する原理と物質を区別する理気二元論です。理とは万物を貫く秩序・原理、気とはそれを形にする素材です。そして人間の本性は理に基づく善なるもの(性即理)であるが、現実の人は気のはたらきによって私欲にとらわれ、本来の理を発揮できなくなっていると考えました。
そのため朱子は、自己の内なる理に従うための修養として「居敬」と「格物致知(窮理)」を重視しました。前者は心を静め、私欲を抑えること。後者は事物の理を探究し、知を深めることです。この二つを通して理と一体となることを目指し、修身・斉家・治国・平天下の道を開くと説きました。
そして明代になると、朱子学を批判的に継承した思想家王陽明が登場します。彼の思想は陽明学と呼ばれ、中心となる考えは「心即理」です。人間の心の本体こそが理であり、善悪を判断する能力である「良知」がすでに心の中に備わっているというのです。
王陽明は「知ること」と「行うこと」は本来一体であると考えました。これが有名な知行合一の思想です。いくら知識を得ても、それを実行しなければ真の理解ではない。良知に従って生き、実践によって自己を完成させること――それが王陽明の教える人間の生き方でした。
まとめ
まとめ
- 孟子:性善説・四端の心・王道政治・易姓革命。
- 荀子:性悪説・教育による矯正・礼治主義。
- 朱子学:理気二元論・性即理・居敬・格物致知。
- 陽明学:心即理・良知・知行合一。
- 入試では孟子と荀子の対比、朱子と王陽明の違いが頻出!
次回は老荘思想について解説していきます。中国思想で狙われるトップ2の内容ですので、儒家思想とは区別して覚えていきましょうね。では、次回もお楽しみに!
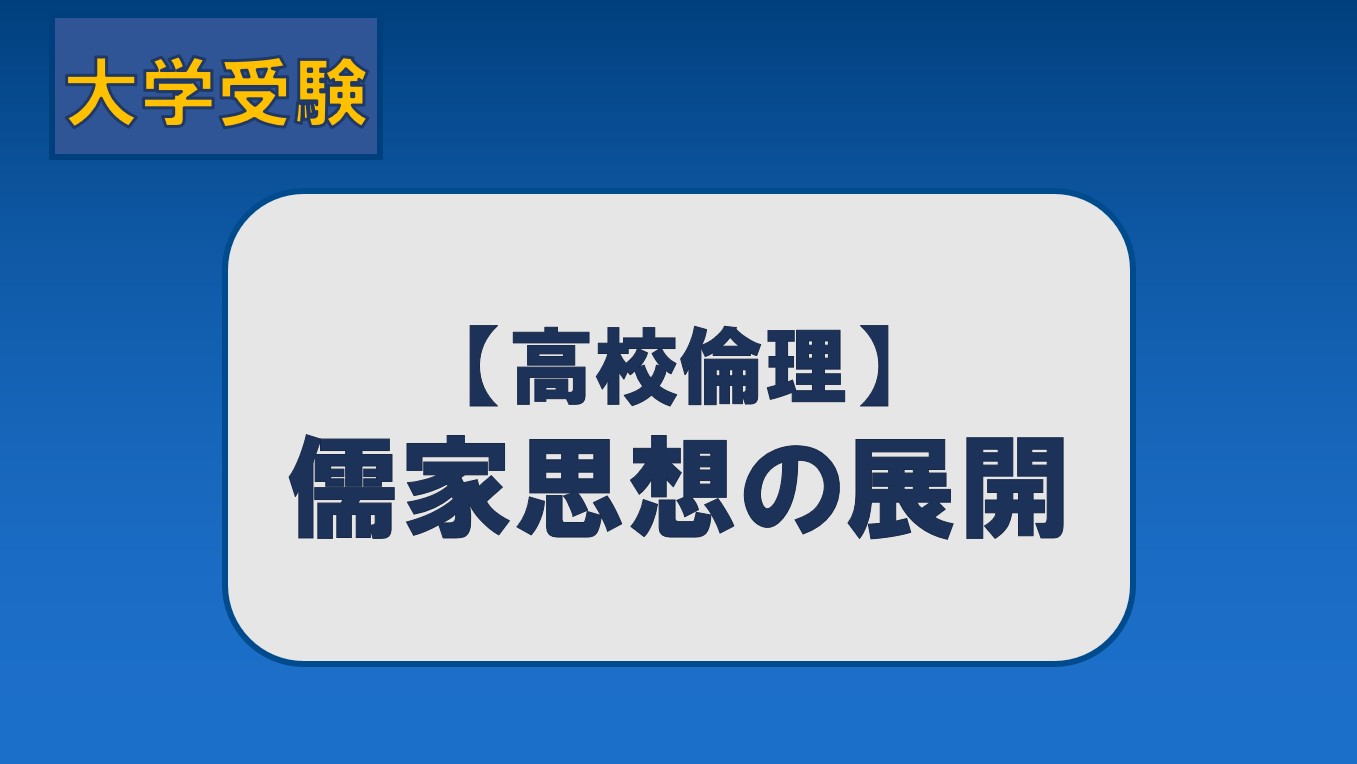

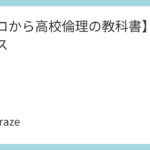



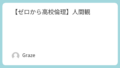
コメント