なぜそもそもこの問題を選んだのか
最近、2025年度の地理の問題をチェックしていると、早稲田大学(教育学部)の地理でこのような問題が出題されていました。
早稲田大学(2025・教育学部) 第2問
問3 下線部②(注:多民族社会)に関して、移民のもたらした様々な文化は融合し、新たな文化を生み出すことがある。下記の音楽ジャンルのうち、アメリカ合衆国が発祥とされているもの全てを選び、その記号をマークしなさい。
イ.ゴスペル ロ.サンバ ハ.ジャズ ニ.シャンソン ホ.ボサノヴァ ヘ.レゲエ
ということで、この問題が出てきた記念(といっても受験生にとっては記念どころか悪魔みたいな問題ではあるが)として、この記事を書いてみようと思います。
どのあたりが悪問なのか
早稲田大学(2025・教育学部) 第2問
問3 下線部②(注:多民族社会)に関して、移民のもたらした様々な文化は融合し、新たな文化を生み出すことがある。下記の音楽ジャンルのうち、アメリカ合衆国が発祥とされているもの全てを選び、その記号をマークしなさい。
イ.ゴスペル ロ.サンバ ハ.ジャズ ニ.シャンソン ホ.ボサノヴァ ヘ.レゲエ
なぜこの問題が悪問かを端的に言えば、地理で取り扱いがないからである。試しに、この手の試金石となる地理用語集を開いてみよう。
新課程の地理用語集で見てみると、そもそもこの中で取り扱いがあるのはロのサンバとハのジャズのみである。ジャズはアメリカ発祥の音楽として知られており、解答としてハのジャズが選ばれないといけないことは疑う余地がない。しかし他のゴスペルだとか、シャンソンだとか、ボサノヴァ、レゲエに関してはもはや知識すらない受験生もいたのではないだろうか。
しかも解答が「全て選べ」なので、個数の制限で何とか切り分けていくことも不可能である。なぜこれを地理で出題したのか理解に苦しむ。なお解答はイのゴスペルとハのジャズを選べば正答である。ちなみに吹奏楽のアンサンブルでは「ゴスペル・タイム」と呼ばれる曲があるが、吹奏楽経験者全員が知っている曲ではない。他のシャンソン、ボサノヴァ、レゲエに関してはその筋に詳しい人しか知らないだろう。私もシャンソンについては知らなかった。
追記:ボサノヴァについてはサンバの説明の項にて説明があった。
さて、早慶でこの手の問題が出てきたときにはおおよそ旧課程の用語集を見てみるとヒントが載っていそう。ということで調べてみると、まったく新課程の内容と変わりなかった。つまり、完全な用語集収録外である。地理受験者はおおよそ地理で高得点を取りに行くわけではないため、用語集に載っていないならほとんどの受験生は知らないだろう。どうしようもない。
そこで気になったため、他の参考書も参照してみることにしたが、全くもって収録なしである。逆になぜラテンアメリカの領域でこの問題を出したのかがなおさらわからなくなる。「地理の研究」を見ても収録がないため、そもそも地理でこのような問題を出題されることが想定外である。
地理で音楽を取り扱う是非
私個人としては地理で音楽を取り扱うのは最低限にしてほしいと思っている。というのも、地理の問題として考えるならば、象徴的なもののみを扱わなければほとんどの音楽ジャンルを網羅しなければならないためである。用語集で言えば、サンバとジャズは多民族社会という文脈では扱っても良いと考えているが、他の選択肢に関しては取り扱わない方が良いだろう。
なお先に言っておくが、現地の音楽を冒涜する意図はない。あくまでも地理教科書の内容だとか、地理での受験を考えたときに収録する/しないの議論である。ついでに言えば、世界史の用語集では音楽史が割と削減されている。そのことを考えれば、地理でも音楽の取り扱いをここまで過剰にする必要はないだろう。
もちろん「ほぼ出る見込みのない問題だから捨て問で良いだろう」という意見も承知しているが、「大学入試で選抜機能に欠いた問題を出題している」ことにも問題があることは留意いただきたい。受験生のメンタルにも関わる問題なので、ここは強調しておくこととしておく。
まとめ
正直なところ、早慶の世界史については『絶対に解けない受験世界史』で稲田先生が解説しているので、用語が細かすぎる/悪問がある/出題ミスがあるなどの問題はしばしば言及される。しかし、このようにして見てみると地理にも割と難問が多くある。それらについては他の記事にて立項して取り上げていきたいと思う。
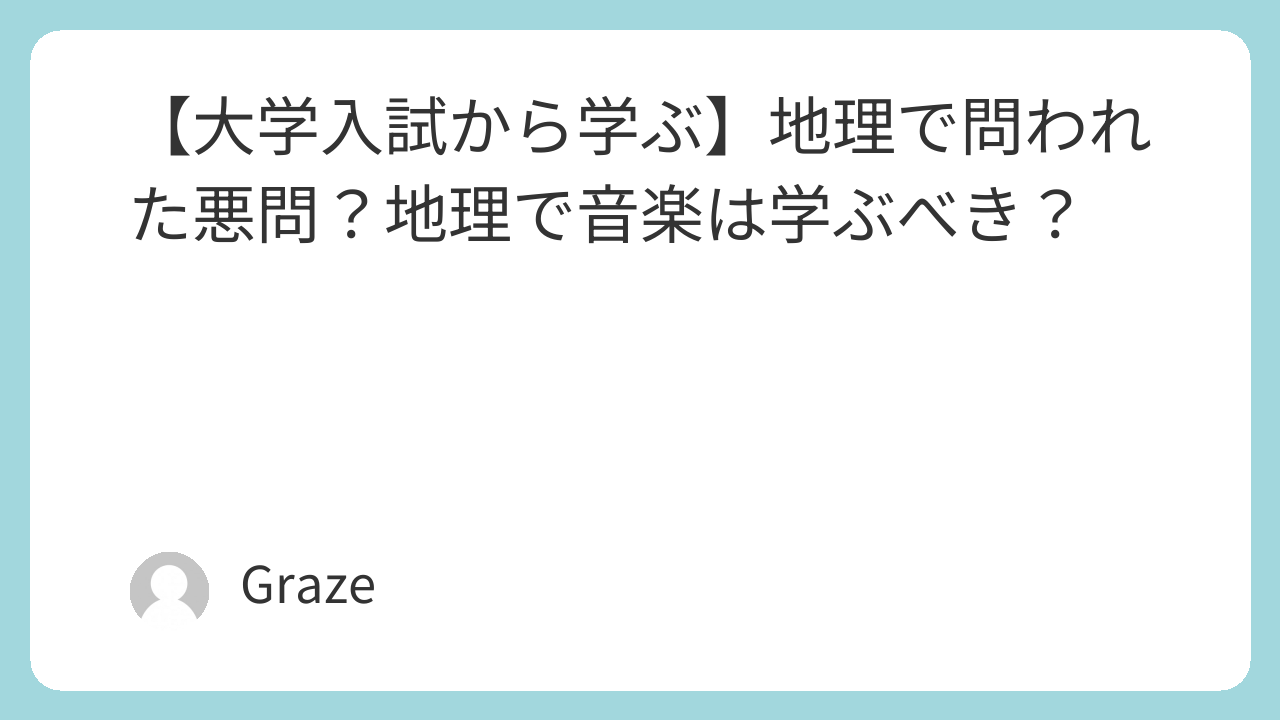

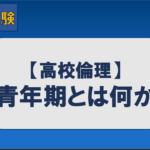
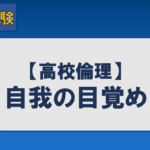
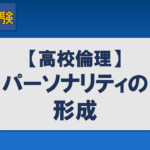


コメント