この記事が対象としている方
- 大学入試で政治・経済/公共を使う受験生
- 定期テストや日常学習で「政治と法」について学んでいる高校生
- ニュースを見て「政治って結局何なの?」と疑問に思っている人
【この記事のキーワード】
政治の意義、権力、支配の正当性、マックス・ウェーバー、国家、主権、法、イェリネック、自然法、実定法、夜警国家、福祉国家
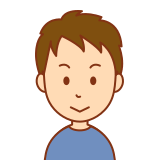
政治って、難しそう…でも身近なところでも実は政治は動いているんだよね?
政治とは何をするもの?
「政治」は国会や選挙だけを指す言葉ではありません。クラスの話し合い、部活動の方針決定、地域課題の解決など、社会の秩序を作り、必要な政策を決める仕組み全般を意味します。
利害や意見の違いによる対立を調整し、全体の秩序を保つために、政治には政治権力が関わります。
支配の正当性 ― マックス・ウェーバー
ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、支配が成立するには人々がその支配を正当だと認める必要があるとし、正当性を次の3つに分類しました。
- 合法的支配:法に基づく支配(例:近代国家の官僚制、近代民主政治)
- 伝統的支配:伝統や慣習に基づく支配(例:君主制、天皇制)
- カリスマ的支配:特別な資質・能力に基づく支配(例:預言者・英雄・扇動的政治家)
現代日本の統治は法に裏づけられた合法的支配の典型であり、法こそが政治の正当性の土台となっています。
政治と国家 ― なぜ「国家」という枠組みが要る?
社会全体の秩序を作るには、個々の集団を超える国家という枠組みが必要です。法学者イェリネックは国家の要件として「領域・国民・主権」を示しました。このうち主権は次の三つの意味を持ちます。
- 国家権力:立法・行政・司法の総称
- 最高独立性:対外的に独立していること
- 国政の最高決定権:国のあり方を最終的に決める権力
国家の意思決定と執行にあたる機関が政府であり、政府が社会秩序のルールである法を作り、運用します。
法の役割 ― 最小限の道徳を明文化する
法は、国家権力の強制力をともなう社会規範で、主に人の行為を規制します。これに対し、道徳は内面を規律しますが国家の強制は伴いません。イェリネックは法を「最小限の道徳」と表現しました。また、法は基本的人権の保障=国家権力の制限という機能も持ちます。
- 自然法:人間の本性・理性に基づく普遍的原理
- 実定法:人間の行為によって作られた具体的な法(成文法/不文法)
- 公法:国家と国民の関係を規定する法(憲法・刑法・訴訟法など)
- 私法:私人間の関係を規定する法(民法・商法)
- 社会法:公共利益や弱者保護を規定する法(労基法・独占禁止法・消費者法など)
なお、法は主権者である国民が代表者を通じて制定し、必要なら改正できます。ただし憲法のように特別の手続を要する場合があります。例えば、憲法改正の発議や国民投票などですね。
国家をどう捉える? ― 起源・本質・機能の理論
国家の成り立ちや性質、役割については多様な理論が提案されてきました。
- 起源:王権神授説(フィルマー/ボシュエ)・社会契約説(ホッブズ/ロック/ルソー)・国家征服説(オッペンハイマー)
- 本質:国家有機体説(スペンサー)・国家法人説(イェリネック)・階級国家論(マルクス/エンゲルス)・多元的国家論(ラスキ)
- 機能:消極国家→福祉(積極)国家(社会的弱者の保護・再分配)
とくに消極国家から積極国家への移行は、失業・貧困などの社会問題に国家が積極的に対応する必要から進みました。現代では、両者のバランスをどう保つかで各国がさまざまな方向に舵を切っています。
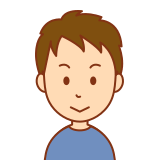
ここは個別試験で狙われるところですね!
学習のヒント
学習のポイント!
- 「政治=社会の秩序づくり」と押さえると、今後の学習が上手くいく。
- ウェーバーの三類型は正当性の根拠を問う頻出テーマ。日本は合法的支配が基本。
共通テストでは具体例と結びつけて答える問題が多い。 - イェリネックの国家の三要素(領域・国民・主権)は用語だけでなく中身(主権の三義)までしっかり抑えておく。共通テストで頻出。
まとめ
- 政治:秩序づくりと政策決定の仕組み
- 支配の正当性:合法的/伝統的/カリスマ的支配(M.ウェーバー)
- 国家の三要素:領域・国民・主権(イェリネック)
- 法の役割:行為を規制する強制力/最小限の道徳
- 国家の機能:消極国家→積極国家
政治と法は、私たち一人ひとりが「どんな社会で生きたいか」を形にする装置です。基礎概念を押さえ、ニュースや教科書のトピックを結びつけて理解を深めていきましょう。
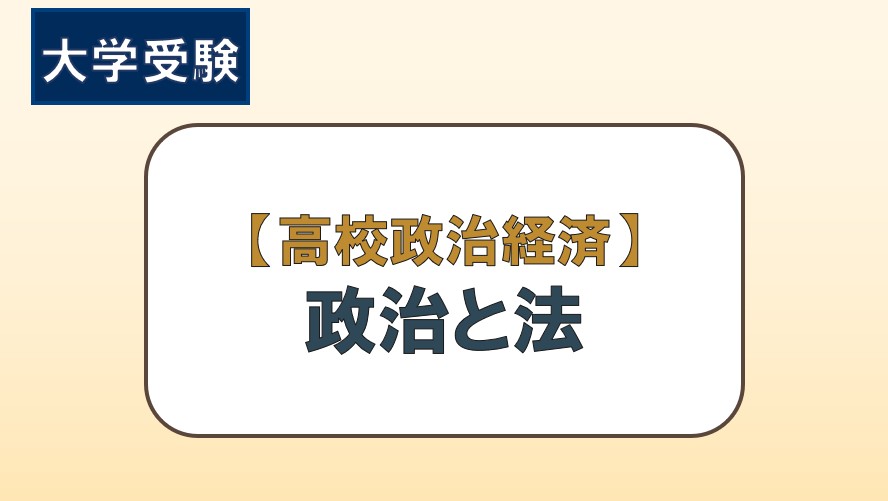
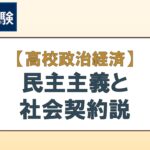

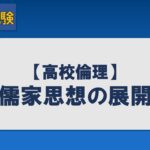
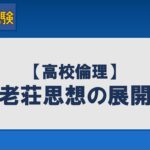
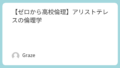
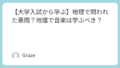
コメント