このページを読むとわかること
このページを読むことで、以下のことがわかるように書かれています。
- 2030年の学習指導要領の改訂で重要視されている3つの柱
前提知識
この記事では前提知識として、次のことを知っている前提でお話を進めていきます。
- 学習指導要領は教育課程の最低基準を定めるものである
- 学習指導要領には10年に1度大きな改訂が入る
もし、「わからないよ~」という方がいれば、こちらの記事で学習指導要領について詳しく説明しています!ぜひご覧ください!
新学習指導要領では何が重要視されているの?
新学習指導要領もいよいよそれぞれの教科・科目の部会で協議されるようになりました。まずは、どのような視点が重要視されているのかについて、リストアップしてみました。
- 「主体的・対話的な深い学び」の実装
- 多様性の包摂
- 実現可能性の確保
現在の日本教育には、様々な課題が残されています。例えばですが、学力調査においては社会的な課題と結びつけて自らの学びを考える力に課題があるとされてきました。このような意味で「主体的・対話的な深い学び」をいかに実行していくのかが重要となっています。
また、クラスの中には6人程度、特別な教育的ニーズをもつ子ども(発達障害の子ども、不登校の子ども、外国籍の子どもなど)がいるとされています。そのような子どもたちを置いてけぼりにしないように、どのように多様な子どもたちを教育の場において包摂するのかという、「多様性の包摂」が重要となっています。もちろん、ただ多様性を包摂しようとするのではなく、何のために包摂するのかがすごく大事になっています。
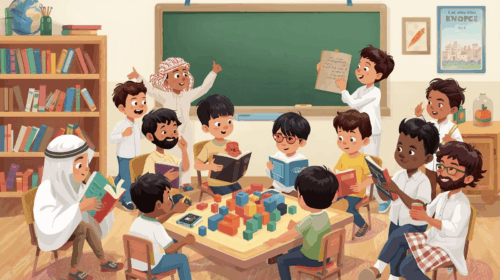
しかしながら、これらの施策は実現できなければ意味がありません。そのために「実現可能性の確保」が重要となっているのです。これは先の「主体的・対話的な深い学び」や「多様性の包摂」を実現するための方向性です。
これら3つの柱を三位一体的に通底させる必要があります。すなわち、これらは単独で進められるべきではなく、一体となって推進されるべきものなのです。このことを文部科学省は「多様な子供たちの『深い学び』を確かなものに」と表現しています。
また、教育の主役は子どもたちですが、その子どもたちを育てるのは誰でしょうか。一般的には保護者か教職と答えられる質問ですが、文部科学省は「みんな」で育てるという点を強調しています。つまり、保護者、教職のほかに地域の人たち、社会に参加している人たち全員で、子どもたちを育て上げるということが大切とされています。
「実現可能性の確保」に思うところ
少し私が思うところを話させてください。私は実を言うと、現行の学習指導要領があまり好きではありませんでした。
大雑把に教科・科目で取り扱う内容はまとまっているけども、逆に言えばそれ以外のことはあまり書いていませんでした。もちろん留意事項なども書いてありましたが、あまりにも現場に即していない留意事項も多々あり、教職として現場に立ったときはこれらに苦悩していた時期もありました。
以前にある記事でお話しさせていただいたんですが、教職の技量はその先生によってそれぞれです。そして、私のような若手の教職は必ず指導書を読んで、どのような授業がいいのかについて研究していました。しかしながら、それは指導書を読んでもすぐにわかるような類いのものではありません。それにも関わらず、学習指導要領にはさまざまな内容を詰め込まれてしまい、ほぼパンク寸前でした。本当に「実現可能性」というものがなかったといえます。
おそらく、新学習指導要領で「実現可能性の確保」の方針が示されたのも教職の負担軽減などを通じて、子どもたちを持続的に育てていくことが目的なのでしょう。であれば、教職の未来、ひいては子どもたちの未来のためにも、この三位一体の改革が推進されることを強く望みます。
どんな子どもを育てていくの?
最後に、新学習指導要領で子どもをどのように育てるか、そしてどんな子どもを育てるかについて、軽くふれて終わりにしたいと思います。
現代の子どもたちに求められる能力として、2つの要素から整理しています。1つ目は「好き」を育み、「得意」を伸ばすこと、2つ目は当事者意識を持って、自分の意識を形成し、対話と合意ができることです。これについてはこちらの記事で、どのような課題があるのかについてふれていますので、ぜひご覧ください。
まとめ
- 「主体的・対話的な深い学び」の実装
- 多様性の包摂
- 実現可能性の確保
まとめとしては上の通りです。これらを三位一体的に進めることで、次の日本型教育を私たち自身が創り上げていく必要があるということですね。
次の記事では、このそれぞれの視点について、地歴公民ではどのように扱われているのかについて、批判的な視点で見つめてみることにします。つまるところ、「現場の私たちはどう考えるの?」ということです。
では、また次の記事でお会いしましょう!

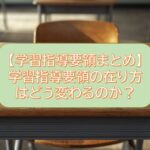

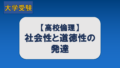

コメント