このページを読むとわかること
このページを読むことで、以下のことがわかるように書かれています。
- 2030年の学習指導要領の改訂での子どもたちの実態と課題
前回の復習
- 学習指導要領は最低基準を定めていて、科目ごとの内容についても定めている
- 社会の変化に対応するため、10年ごとに改訂される
現在の学習指導要領は変わらなくていい?
前回では、学習指導要領の概要について学びました。
今回は、2030年の学習指導要領に向けて、どのような議論が必要となるのかをまとめてみました。といっても、今回焦点をあてる資料は「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」と呼ばれるものです。(リンク先はpdfファイルですのでご注意ください)
前回では、社会の変化に対応して学習指導要領が改訂されることについて触れました。
では、現在の学習指導要領は変わらなくていいのでしょうか?
さらに言えば、現在の学習指導要領は最善と評価されているのでしょうか?
子どもたちの現状と課題
学習指導要領等は、こうした経緯で改善・充実が図られてきた。改訂に当たって議論の出発点となるのは、子供たちの現状や課題についての分析と、これから子供たちが活躍する将来についての見通しである。
「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」(文部科学省)
改訂にあたっては、現在の子どもたちがどのような現状であり、どのような課題があるのかを明らかにしなくてはならないでしょう。それは先に引用した「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」でも明らかとなっています。
内閣府の調査によれば、子供たちの9割以上が学校生活を楽しいと感じ、保護者の8割は総合的に見て学校に満足しているとされています。このような現状は各学校において、真摯な取組が重ねられてきたことの成果として評価されています。
一方で、学力に関する調査においては、次のような能力や意識について課題が指摘されています。
- 判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べられるか
- 実験結果を分析して解釈・考察し説明できるか
- 学ぶことの楽しさや意義が実感できているか
- 自分の判断や行動がよりよい社会につながるという意識をもてているかどうか
こうした調査結果からは、能動的に学ぶことに課題があるといえるでしょう。
能動的に学ぶことは、現行の学習指導要領では「主体的・対話的な深い学び」として表現されており、現行の学習指導要領において重要視されていることでもあります。
そのような意味において、学ぶことに対する楽しさや意義が実感できていないというのは現行の学習指導要領の課題であるといえます。
また今後大きく変わりゆく社会では、社会の中で出会う課題と正対することも多いでしょう。そこで自分の判断や行動がよりよい社会につながる意識を持てていない子どもがいることも課題の一つとなります。
現場で教職をやっていたときの経験より……
実は、私には現場で教職を経験していた時期があります。その経験のなかでも子どもたちには様々な課題が見受けられました。
最初は、社会科のなかで「学んだことを自分で文章化」してみるという訓練をしていました。しかし、最初に出してもらった課題の内容を見ると、文章として成り立っていないというケースが多々みられたのです。例えば、文章を読んでみると主語がないだとか、文章で答えてほしいと要求しているのにもかかわらず、単語1つで解答しているだとか……。
この状態だと、もはやどこから切り込むべきかすらわかりませんでした。なので、様々な手段を講じていました。
- 課題の形式を紙媒体のプリントで出させるようにする
(GoogleFormで提出させると、文章全体が見にくいため、確認を促す意味でも紙媒体のプリントで出させました) - 授業内でも文章で自らの考えを表現する場を設ける
(例えば、産業革命のころの資料を提示して、当時の労働問題について記述させたり……」 - 歴史と現在のつながりを明らかにする
(歴史の構造を単線的にとらえるべきか、複線的にとらえるべきか、多面的にとらえるべきかを、必ず授業の最初で示すようにする)
すると、提出させた課題にも改善がみられるようになりました。文法の破綻もすごく少なくなり、自分の考えを文章だけではなく、図などを用いてさらにわかりやすく表現している生徒もいました。そのような意味で、前に挙げた試みはある程度成果を挙げたのかもしれません。
しかしながら、それはどこの学校でもできることではありません。いわゆる生徒観(生徒の実態)が異なるからです。したがって、まずは最低基準とされる学習指導要領を踏まえ、子どもたちの実態を概観しておくことが、すべての子どもたちを包摂するために必要なこととなります。
本記事のまとめ
ここまで現在の子どもたちの実態と課題とはどのようなものなのかについて、説明していきました。
要点は以下の3つです。
- 現行の学習指導要領では能動的に学ぶ「主体的・対話的な深い学び」の実現をめざしている
- 子どもたちの学んでいることへの目的意識に課題があるとされている
- 学習指導要領ではすべての子どもたちを包摂することが必要である
次回も、2030年の学習指導要領に関する議論を眺めながら、次の学習指導要領に何が必要かを考えていきましょう。
では、次の記事をお楽しみに!


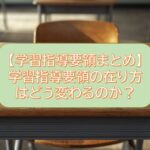
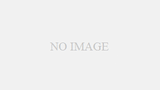
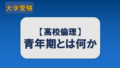
コメント